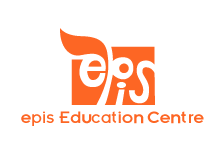深センのSTEM教育の現状(PBLの実践)
先日、深センにいながらもアメリカの最新のSTEM教育の現場を見る事ができるということで、深セン市南山区にあるSAIS(Shenzhen American International School)を訪問させていただきました。
同校では、問題解決学習(PBL:Project Based Learnig)を学校全体で採用しています。PBLでは、日本の教育の中心である、先生が生徒に対して「教える(teaching)」教育ではなく、生徒が自ら「学ぶ(learn)」姿勢を最重要課題としています。
見学した5年生の時間割は、Humanities、Math/Science、Chinese、Art/Maker/PEの4教科に大別され、生徒たちはこの時間の中で自分の興味を持ったことから自分のProjectを決定します。また、どの教科も常に横断的な学習を行っており、Humanitiesで気づいた統計的な問題があれば、それをMath/Scienceの授業に持ち込んで、問題解決をしています。ここには「算数・数学が一体何の役に立つの?」という日本ではよく聞かれる質問も愚問という他ありません。
ある生徒はHumanitiesの時間で歴史上の人物に興味を持ったので、 自分のアイディアを生かしてUnityを使ってゲームを作ったとのこと。つまりUnityを教え込んだ後に、何を作るかを考えるのではなく、何かゲームを作りたいと思った生徒にUnityを与えるというシステムです。
3年生のクラスでは、ダンボールで椅子を作るプロジェクトを進行中でした。一見すると粗末なダンボールで作られた椅子が制作途中なのですが、ここで重要なのは、まず生徒に作らせてみること。作った椅子に座ってみるとすぐ潰れてしまったり、背もたれが折れてしまったりしたときに、どうすれば耐久性が高められるのかを考えます。このときも先生が指示をするのではなく、あくまでも生徒から自発的かつ具体的な質問があったときに、先生が初めて動きだします。それも、解答を与えるのではなく、生徒が能動的に解決できるようなヒントを与えます。
物を作ることが目的なのではなく、物を作る過程で問題点を自ら発見し、それをいかに解決していくかを重要視しているということです。
私自身、中学生の時に、木材を使って折りたたみのできる椅子を作ったことがあります。設計図通りに木材を切って組み立てるということでした。ダンボールの椅子と木材で作った椅子を比べたら、完全に木材の椅子の完成度が高いわけですが、その制作過程で得られた問題解決能力向上の機会は、やはりPBL方式に軍配があがると思われます。
SAISには「Maker」の授業が、日本の学校には「技術家庭」の授業があり、物を作ってみるという点では全く同じであるのに、その底流に流れる思想と目的が全くことなるため、教育の成果が大きく異なってきています。
日本でも「STEM教育」「プログラム教育」という言葉盛んに聞かれるようになってきました。どちらの教育もすぐに初めたらいいのですが、そこで注意しなければならないのは、いずれの教育にも根底には「自ら問題を発見する」「自ら考え問題を解決したいというモチベーション」が必要だということで、それら無しにはこの教育を初める価値が激減してしまうということです。
これは、STEM、プログラムに限ったことではなく、現状の学習教科である、国語、数学、英語などの学習においても、いかに生徒たちのモチベーションを高められるかが教育上の最も大きな課題だと言えます。STEM、プログラム教育の導入をきっかけに、日本の教育のあり方を見直す機会になればと思います。