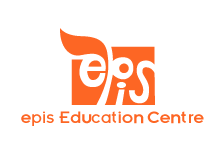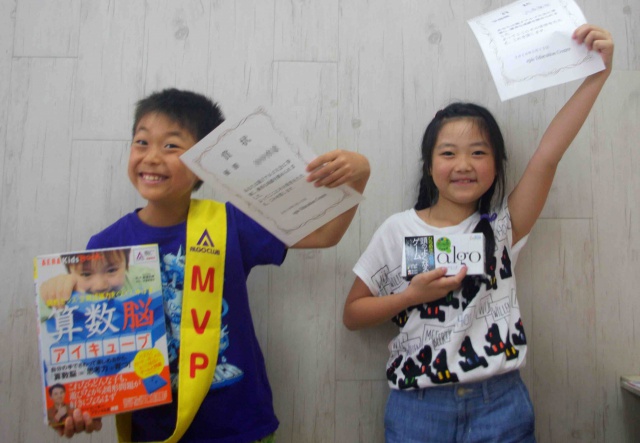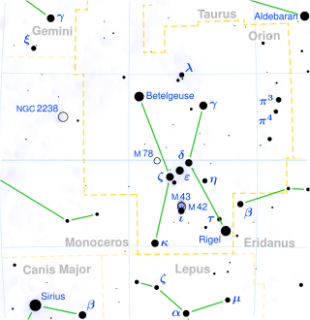去る10月31日(土)、海外実施の2016年度入試の初戦、土浦日本大学高等学校の帰国入試がアジア6都市で実施されました。
土浦日大の入試は、11月前後に受験できるという日程的な要因や寮を完備していることから海外からの受験生を多く集めています。
合否結果もその得点により進学、特進、2種特待、1種特待、1種S特待と5段階に分かれるため、秋の段階での仕上がり具合を確認するという意味でも多くの海外生が前哨戦として受験しています。
今年の入試は、昨年度の本校の大学合格実績の伸び(東京大学、筑波大学)を受け、難化を想定していましたが、想定通りに英語を筆頭にこれまでとは大きく異なる入試となりました。
この難化は本校の大学合格実績に対する自信の表れと、入試そのものの格式を上げることで、学校そのもののブランド力アップにつながっていると思われます。
英語圏やインターからの受験生であれば、今回の英語の難化は歓迎するところですが、非英語圏の日本人学校の生徒にとっては英語で差のつく試験となり苦戦したことと思います。
1月の国内帰国生入試、来年度の入試の参考にしていただければと思い、各教科の具体的な変更点や試験内容の特徴、対策について以下にまとめました。
国語
【構成】
大問1語彙・文学史などの知識問題/大問2論説文/大問3小説文/大問4詩/大問5古典
構成は例年通りで大きな変化はありませんでした。全体の特徴としては、大問1以外でも知識問題が目立っています。例えば大問2で品詞の識別、3大問で四字熟語、大問4で表現技法・部首・ことわざ、大問5で文学史、などが出題されています。
【分析・対策】
読解問題の選択肢は紛らわしいものもあるので、普段から吟味して選択肢を選ぶくせをつけておく必要があります。(例えば選択肢の文中の心情語、理由部分、その他キーワードなどに着目し、根拠づけながら選択肢を切っていく)
最後に、古典は出題できるものも限られてくるので、代表作は粗筋だけでも目を通しておくと良いでしょう。宇治拾遺物語、今昔物語、徒然草などが一般入試も含め過去に複数回出ています。(今回は「今物語」)
数学
【構成】
大問1小問集合/大問2確率・文章題(速さ)/大問3文章題(食塩)/大問42次関数/大問5平面図形(相似・円)
構成は例年通りとなっていますが、やや難化傾向にあります。
【分析・対策】
大問1の小問集合は例年では満点を狙える得点源でしたが、単純な計算ではない不定方程式が出題され序盤でつまずき焦った受験生が多かったのではないでしょうか。
大問3の文章題は食塩水の問題でも有名な等量交換の問題が出題されました。比を利用して解けばいとも簡単に解くことのできる問題ですが、食塩の問題が苦手な人にとっては難題となったことでしょう。
大問5の平面図形は、例年通りで難易度もさほど高い問題ではありませんが、学校であれば9月・10月に学習するので、習ったばかりの受験生にとっては難しいとも言えます。
対策としては、2次関数、相似が例年出題されていますので、学校での学習を待たずに夏までには基礎的なレベルの問題が解けるようにしておきましょう。また、例年は見られなかった速さ・割合の文章題も出題されているので、文章題の対策も怠らないようにしましょう。
英語
【構成】
大問1・2読解/大問3会話文/大問4発音・アクセント/大問5並び替え/大問6・大問7空所補充
問題の順序は年によって前後することもありますが、読解力/文法・語彙力/発音と幅広く問われる点はこれまでと変わりありませんでした。
【分析・対策】
大きな変更点としては、大問1・大問2の読解問題の長文が非常に長くなっていることや、大問3の会話文が長文の中に組み込まれるなど、全体を通して読まなければならない英文量がかなり増えていまることです。これまでの過去問と同じペースで進めていくと時間不足になってしまいます。全体としては難化傾向と言えます。
対策としては、まずは普段から長めの文章問題に慣れておくことが`第一ですが、他には問題形式ごとに取り組みを工夫すると良いでしょう。例えば大問2のタイプは一気に読まずにパラグラフごとに問を確認する。選択肢に細かいひっかけがあるので、狭い範囲で根拠を明確にしながら解いていった方が間違えにくくなります。また大問3のような問題は、全体を読まなくても空所の前後の手がかりだけから答えることができます。そういった取り組み上の工夫からもかなり時間を稼ぐことができるでしょう。
土浦日本大学高等学校 帰国国際生入学試験情報
海外入試
日程:2015年10月31日(土)
試験地:台北、香港、バンコク、上海、シンガポール、ジャカルタ
試験科目:国語・数学・英語(各50分マークシート方式)・面接(受験生のみ)
合格発表:2015年11月9日(月)
国内入試
日程:2016年1月16日(土)
試験会場:土浦日本大学高等学校
試験科目:国語・数学・英語(各50分マークシート方式)・面接(受験生のみ)
合格発表:2016年1月20日(水)