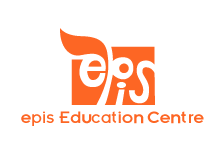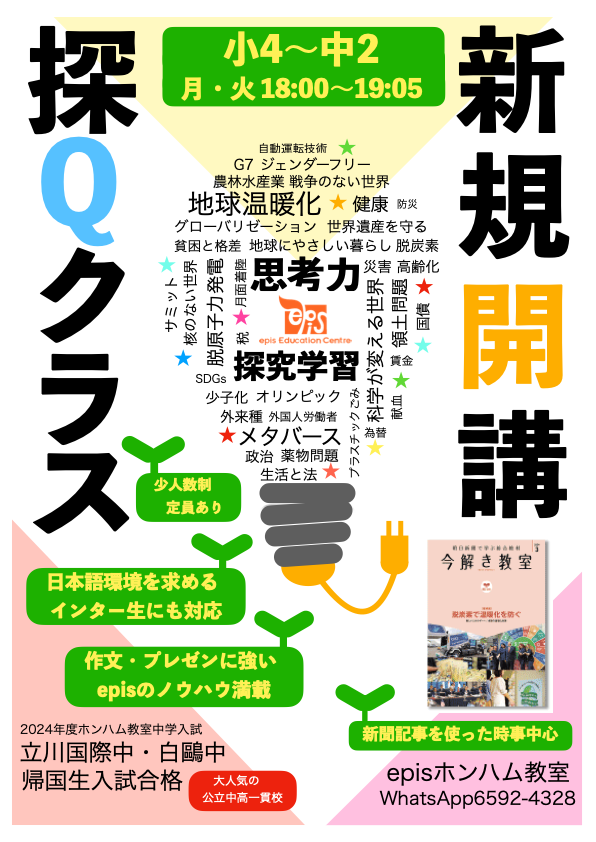算数
【授業内容】
第7回 売買損益
物を売ったときの売り上げ・利益・損失などの問題です。そこに割合が関連してきますのでより難しく感じることと思います。ただし、このように様々な場面で割合に触れていくことで慣れていくことも重要なので、ぜひくじけずに立ち向かってほしいです。
まずは、重要な用語の確認です。文章題を読んでイメージができないと当然図や式も立てられないので、ここからしっかりと理解しましょう。
仕入れ値(原価)・・・ものを手に入れるための値段
定価・・・初めに着ける値段
売値・・・実際に売った値段(定価と同じこともあります)
利益・・・もうけの値段 利益 = 売値ー仕入れ値(原価)
損失・・・損した金額 損失=仕入れ値(原価)ー売値 売値<仕入れ値(原価) のときに使う
売り上げ・・・売値の合計。「1日の売り上げ」とか「1か月の売り上げ」とか、「全体の売り上げ」とか、複数のものが売れたときに、その売値の合計として考えます。
(例題1)割合と言葉の練習
仕入れ値・売値・利益などの言葉の使い方の確認です。
それらの量のイメージをつかむために、ぜひ線分図を描けるようにしたいです。
慣れてくれば、描かなくてもできる「定番形」もでてきますが、まずは複雑になったときに線分図を描けるようにするためにも、この基本的な問題レベルで、正確に描けるように練習したいです。
解けない場合は、テキストの線分図をよく見て、「ただ書き写す」のではなく、「ノートに上に考えながら再現する」ことを意識してほしいです。
(例題2)仕入れ値から利益を求める
仕入れ値がわかっている状態で、定価・売値・利益を順番に求めていく練習です。
(例題3)利益から仕入れ値を求める
例題2と違い、初めの仕入れ値が書いておらず、最後の利益がわかっている問題です。
仕入れ値を実際の値段ではなく、割合のもとにする量である「1」を使った状態で表現していって、その割合で利益がいくつと表せるかを表現していきます。
(例題4)異なる2通りの売値から仕入れ値を求める
仕入れ値が隠されていて、値引き率の異なる2種類の売値とそれぞれの利益から、もとの仕入れ値を求める問題です。
小問で誘導がついていて、まずは設定された定価を求められるのだと気付きたいところです。
売値を決めるときに、「定価の~~割引」という表現がでているので、定価を基にする量「1」として売値を表現することで、その2つの売値の差をつくり、それと実際の金額のずれを対応させていきます。
線分図を2本書いて、しっかり比べていくことが重要です。
(例題5)全体の利益を求める
ここからは、複数個の品物を売る問題になります。
全体の利益=売上ー全体の仕入れ値 であることを利用します。
問題の設定は、実生活に近いものなので、1日目・2日目の売値と売れた個数を丁寧に追いかけていきたいです。
【宿題】(3月22日(金)までに解き終わってください。)
・p.72~p.76 例題1~ 例題5
・計算 第7回
担当 東本 tohmoto@epis-edu.com