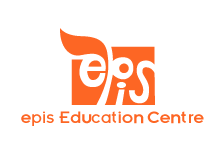4SY 5月21日(火) 授業報告
算数
その中で、特に頻出の「等差数列」がテーマです。
元々、「等差数列」という用語は、日本の学校のカリキュラムで初めて登場するのは高校生ですが、テキストでは当然のように使われています。言葉を難しくとらえるのではなく、「知っていることによって、問題に戦いやすくなる」というイメージで覚えていってもらえると良いと思います。
したがって、高校生が使うのと同じ用語も使って授業をしています。
数列・・・あるきまりに従って並んでいる数字
等差数列・・・ある数(初項)から始まり、ある一定の数ずつ増えたり減ったりしてできている数列
一定の数ずつ増えているとき、その数字を「公差」と言います。
減っている場合も等差数列ですが、小学生は負の数を扱えないので
「~~ずつ減っている」という言い方で表現されています。
(例題1)等差数列の□番目の数
□番目の数字= 初項 + 公差 × ( □ - 1 )
なぜ(□-1)をかけるのか。そのイメージは第12回で扱った「植木算」が良いと思います。
両端に木が植えられているとき、□本の木があるとき、その間の数は(□-1)個ある ことに対応します。
(例題2)ある数字が、その等差数列で何番目にあるか
例題1の式を逆に使う練習です。
□で式を作って、逆算で求められることを基本として、慣れてきたらいきなり□を出す式に変形できるようにしていくと良いです。いきなり出すことにこだわるより、例題1の逆をやっているのだということを理解することが大事です。
(例題3)初項から□番目までの和
こどもたちに自由に解いてもらうと、左端と右端, 左から2番目と右から2番目 ・・・とカップルを作って足していくという方法を取ることが多いです。もちろん思いついていることも素晴らしいし、使いこなせればよいのですが、この方法は数列が「奇数個」の場合にカップルが作れない数字が真ん中に残るため、どうしてもそれを見落としがちになります。
そこで、テキストでも「数列の和の式を逆順に書いて、必ず等しくなる縦の組み合わせを足していく」という方法の理解を大事にしていますし、授業でもそのように教えています。
安易に「両端どうし・2番目どうし・3番目どうし」とやらずに、この仕組みを理解したいところです。
逆順に書いてたての組を作ると、なぜその和が等しくなるのかも、必ず理解したいところです。
上の数字は5ずつ増えていくのだから、逆順に書くと5ずつ減っていくはずなので、左端のたての組と2番目のたての組は和が等しくなる これを理解している生徒は、今日の授業でも複数名いました。
公式があるとき、それが「なぜなのか」を考えることで、より理解が深まる典型だと考えます。
(例題4)1から始まる奇数の和
1から始まる奇数の数列があるとき、
・□番目の数字=2×□ - 1
・1+3+5+・・・+(2×□-1)=□×□
これらは、何かを平面的に並べていくような問題でとてもよくつかう大事な知識になるので、覚えることが多くなりますが、必ず身に付けていきたいところです。
今回の1回のみで完璧に身に付けるのは難しいですが、これから出てくるたびに確認していく内容になります。
・今日の内容の復習 テキスト p.130-135 例類題1~4
テキストp.136~137 基本問題1~4
(余力のある人は、p.138,139の練習問題にもチャレンジしてみてください。)
・計算 「第14回」
*テキストには書き込まず、ノートに書いて計算しましょう。
計算途中は必ず残しておいて、間違えたときにどこで間違えたのかを確認できるようにしておきましょう。
担当:東本(とうもと)
tohmoto@epis-edu.com