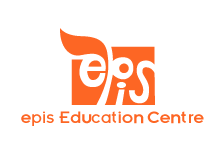6月5日(水)の授業報告
6月5日(水)の授業報告
第2月間(年長) 第2週目
■授業内容
・記憶ゲーム
・ピーキューブ(箱出し、箱詰め競争、ものまね積み木)
・ジオワン(影まねジオ)
・アイキューブ(タワー)
・プリント(詰めアルゴ・ナンバーリンク・チャレペー・迷路)
・アルゴゲーム(3枚ゲーム)
・表彰(MVP:大江くん、マナー王:瀬見くん)
5人全員が最初から最後まで元気いっぱいに取り組んでくれていることがとても嬉しいです。アルゴゲームも、いよいよ全員が自分でカードを並べアタックができるようになり、白熱したゲームとなっています。プリント学習も、みんな少しずつ自分で答えが出せるようになり、早くできた子から分からなくて困っている友だちに親切に教えてあげる雰囲気も出来てきました。ポイントをもらえた時のみんなの笑顔が本当に素敵です。
■自主トレ(宿題)
ピーキューブ・ジオワン(自由に形を作る練習)