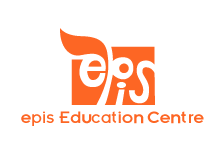算数
第18回 一方におきかえて解く問題(つるかめ算)
受験算数の象徴のように有名なつるかめ算です。
今回の単元が終わった後も、つるとかめの足の数だけではなく、様々な文章題でこれを利用するものが登場することになります。
「もしすべて~~だったとすると」という仮定から、矛盾を引き出し、仮定と実際とのずれを考えて正しい答えにたどり着く という非常に論理的な思考が必要とされるため、初めはなかなか理解できないことがあります。何しろ、初めから正答にたどりつくまでに使う式がとても多いです。
板書でも、みんなが慣れてくるまでは、「もし全部が○○だとすると」「実際の本数とのずれは」「もし1羽のつるがかめに変わったとすると」などの説明を書きながら、どのような流れで解いているのかを示していきます。もしおうちで解いていて「わからない」となった場合は、「今、何の計算をしているのかがわかっているのか」ということを確認してあげてみてください。
(例題1)つるかめ算とは(つるとかめの足の問題)
つるが何匹いるか を問われているので、まずはつるが0匹だとして考えることにします。
つまり「13匹すべてかめだとすると」から始めます。
そのときの足の本数を計算してみると、実際の本数より8本多すぎることに気付きます。
ここで、「もし1匹をかめ から つる に変えると、足の数は2本減る」ことを確認します。
したがって、8÷2=4 で、4匹をかめからつるに変えれば、足の数がただしくなることに気付きます。
つまり、求めたいつるの数は4匹(4羽)とわかります。
この流れをしっかりとつかめるように意識的に練習していきたいです。
(例題2)つるかめ算の利用(代金と個数の問題)
今度は、足の数ではなく、単価の異なる2種類のものの代金で考えていきます。
考え方は例題1とほとんど同じなので、自分でスタートからゴールまで、たどりつけるかを確認します。
(例題3)つるかめ算の利用(弁償算)
今度は、1枚の皿について、「無事に洗うと20円もらえ、割ってしまって洗えないと、20円ももらえない上に50円べんしょうする必要がある」という条件です。
つまり、1枚のお皿を洗えず壊してしまった場合には、もらえるはずだった20円がもらえない ことに加えて、50円払って弁償する ので、そのたびに70円のお金を失っていくことになります。
その70円分が、実際にもらえた金額とのずれに何回分入るか という割り算をすることになります。
(例題4)つるかめ算の利用(弁償算と初期値が0でない問題)
例題3と同じで、1回の勝ちが負けに変わった場合、得点が5点+1点の6点分 減ることになります。
ただし、元々ゲームの初めに30点持っているところからスタートするので、得点を計算するときにそれを忘れないようにする必要があります。
【宿題】
・今日の内容の復習 テキスト p.166-173 例題・類題・基本問題
(可能な人は、p.174~175の練習問題もチャレンジしてみてください。)
・計算 「第18回」
*宿題はすべて答え合わせと直しまで。
*テキストには書き込まず、ノートに書いて計算しましょう。
計算途中は必ず残しておいて、間違えたときにどこで間違えたのかを確認できるようにしておきましょう。
担当:東本(とうもと)
tohmoto@epis-edu.com。