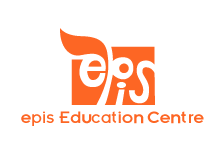5SY理科 6月22日(土) 授業報告
理科
オンライン受講の方へ
以下がアドレスになります。
4076016764 https://us02web.zoom.us/j/4076016764
【授業】
光合成
水と二酸化炭素から、酸素とでんぷん(栄養分)をつくりだす、植物だけが行えるはたらきです。
そのとき、日光のエネルギーをでんぷんのなかにたくわえることができます。
これは、植物自身の呼吸やからだをつくることに使われていく他、動物にたべられることで動物の栄養分としての役割も果たせます。地球上のすべての生物が、植物が作り出した栄養分を呼吸をするために使われるため、とても重要な役割です。
呼吸
すべての生物が行うはたらきで、「生活(生命活動)のエネルギー」を得るために行います。
酸素とでんぷんから水と二酸化炭素ができますので、これは光合成と完全に逆の変化になります。
光合成量と呼吸量
植物は、昼夜を通して二酸化炭素の出し入れをして生きています。
二酸化炭素の吸収量と排出量の関係は、以下のように見えます。
・光をあびて光合成をさかんにしているとき 吸収量>排出量
⇒光合成で使われる二酸化炭素量が呼吸で排出する二酸化炭素量より多いため
・光合成をしていないとき 吸収量<排出量
⇒呼吸で排出する二酸化炭素量のみのため
光合成をしているときも、呼吸をしていないわけでなないことに注意しましょう。
蒸散
植物が、葉や茎にある気孔から水蒸気を排出するはたらきです。
体温調節や、根から水分を吸収するために行います。
「せんたくものがかわきやすいとき」に多く蒸散すると考えればよいでしょう。
【宿題】
演習問題集 第18回
担当 東本 tohmoto@epis-edu.com