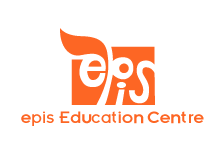オンライン受講の方へ
以下のアドレスでご参加いただけます。
3608057229 https://us02web.zoom.us/j/3608057229
【授業内容】
皆さんの宿題を確認していて気になることがあったので、授業の初めに話をしました。
まず、宿題は「原則ノートに解いて、○付け・直しをしましょう」
扱っている内容はかなり難しいものがありますから、カリキュラムとしても必ず「復習する」ときが出てきます。例えば、来週「第5回」は「総合」の週で、第1回から第4回までの復習を行うことになっています。
それを扱ってみて、解けない問題に出会ったときは、実際にテキストを戻って、章末の「基本問題」やその章の「例題・類題」を解いてもらう必要がでてきます。
そのときに、テキストに直接答えを書きこんでいると、答えがわかった状態のやり直しになり、本当の力が見えなくなります。
また、ノートの宿題が、「計算とテキストの宿題が一緒になっている」人もいます。
それは、できる限り違うノートにやってください。
どちらも算数の内容ではありますが、自分で復習をしたいときにノートを開いて戻りたくても、計算テキストの練習までそこに書いてあると、目当ての部分が見つけにくくなってしまいます。
「ノートに書く」ことは「その場だけの作業をするスペース」から、「必要な時に復習する」「過去の自分の出来を確認して今と比較する」ためのとても貴重な情報の意味を持つようになってきています。
特に、難易度の高いことをやっていますので、復習はとても重要ですので、ぜひご家庭でも、ノートをとる意味と価値を一緒に考えてご協力いただけるとありがたいです。
皆さんには「情報を検索する力の重要性」のお話もしました。ノートで以前解いたときの「第○章の問△」を探そうとしたときに、見つけるまでに時間と手間がかかると、勉強の効率が非常に下がります。
章のタイトルやページ・授業の日付などを残して、探すときの手掛かりになるようにしておきましょう。
・予習シリーズ 第4回「和と差の問題」
やはり今回も言葉から。
和…たし算の答え 差…ひき算の答え 積…かけ算の答え 商…わり算の答え
今回の章では和と差を使いますが、積と商も一緒に覚えてしまいましょう。
例題1 線分図の利用・和差算(大きい方を求める)
例題2 線分図の利用・和差算(小さい方を求める)
まず線分とは、「両端が止まっているまっすぐな線」のことで、算数(数学)では、「直線」と区別して使います。
そして、線分図とは、「長さで量を表して比べる図」のことです。
問題に2つ以上の量の大小が出てきたときに、線分図を使ってそれを図示することができます。
問題文が複雑になるほど、頭の中だけでは考えきれなくなるので、線分図に表現して考えやすくするために描きます。
どんな問題でどんな図にすると考えやすくなるかは、経験を積んでいくことが大事です。
まずは、テキストに描いてある図や授業で使った図を真似するところから始めましょう。
そして、今回の単元では「そろえる」ことがテーマです。
長い方の線分にそろえる ⇒大きい方の数を求めるとき
短い方の線分にそろえる ⇒小さい方の数を求めるとき
と、図を見ながら考えていくことを意識して練習しましょう。
2つの量の和差算は、まとめると以下のようになります。
【大】・・・大きい数 【小】・・・小さい数
【和】・・・2つの数の和 【差】・・・2つの数の差 と表すと
【大】= (【和】+【差】)÷ 2 ・・・大きい数に線分をそろえて半分にする
【小】= (【和】ー【差】)÷ 2 ・・・小さい数に線分をそろえて半分にする
例題3 平均と和差算
平均・・・いくつかの数(量)を平らにならした値
平均 = 合計 ÷(人数・個数) ⇒ 合計=平均×(人数・個数)
これと和差算を組み合わせた問題です。
例題4 3つの量の和差算
2つの量の時と同じで、3つの量を線分図にして比べます。
問題で与えられた条件は、2つずつの量を比べているので、順番に大小を意識して図にしていきます。
そして、全体をそろえやすい量1つにそろえることを考えます。
どれか1つの量がはっきりすると、残り2つの量も求まっていくはずです。
【宿題】
テキスト p.36 - 43 例題1から類題4 基本問題まで
(できる人は、p.44,45の練習問題にもぜひチャレンジしてください)
計算テキスト 第4回
*宿題はすべて答え合わせと直しまで。
*テキストには書き込まず、ノートに書いて計算しましょう。
計算途中は必ず残しておいて、間違えたときにどこで間違えたのかを確認できるようにしておきましょう。
担当:東本(とうもと)
tohmoto@epis-edu.com